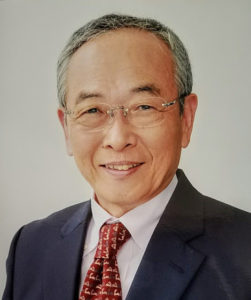喫緊の課題は、すでに指摘されているが、人間がAIに使われてしまい、ビジネスの主権はどちらが執るのかということである。この「AIエージェント」があれば、「使えない部下」や「ダメな上司」と仕事をするよりは、千倍も効率的な仕事ができるだろう。このような分野で人間が主権を取らなくてはならないのは自明の理だが、私は「AIオタク」が主権を取ることはどうしても避けたいと思っている。
現行の生成AI技術は、文章をはじめ画像、動画、そして音声などの生成に物凄い力を発揮している。、またウェブ検索でも従来のネット検索と違い、こちらの質問にその時初めて個別にこたえるかのように、詳細な検索結果を出してくる。まるでPC画面の後ろに回答者がいるようだ。傘寿(80歳)を過ぎ、ビジネスから引退した私ら「昭和の青年」世代にはチンプンカンプンというのが実情であろう。
しかし、驚いてはいられぬ。この度、ソフトバンク・グループは現行の「受動的」な生成A Iのさらに上を行く「AIエージェント」なる「能動的」なAIシステムを社員が業務に活用できるようにしたのだ。「昭和の青年」は居眠りなどこいてはいられない。

出典:トラオ
こうなってくると、喫緊の課題は、すでに指摘されているが、人間がAIに使われてしまい、ビジネスの主権はどちらが執るのかということである。この「AIエージェント」があれば、「使えない部下」や「ダメな上司」と仕事をするよりは、千倍も効率的な仕事ができるだろう。このような分野で人間が主権を取らなくてはならないのは自明の理だが、私は「AIオタク」が主権を取ることはどうしても避けたいと思っている。
【contents】
1. AIエージェントとは
生成A Iの利用が世界で拡大する中、ソフトバンク・グループは、AI(人工知能)が目的に応じて「自律的」に業務を進める「AIエージェント」をグループの社員が業務に活用できるようにする計画を明らかにした(2025.07.16.)。
現行の生成A Iは、人が明確に出した指示(プロンプト)に従って文章、画像、動画、音声などを生成することに特化されている。いってみれば、指示されたことだけを「受動的」に生成する。
これに対して「AIエージェント」は人から詳細な指示を受けなくても、AI(人工知能)が目的に応じて「自律的(能動的)」に仕事を進める技術である。
特定のアプリケーションやサービスに限定せず、複数のタスクを横断的に組み合わせて実行するため 、AI以外にもウェブ検索、外部API、データベースなどのリソースを適宜活用し、最適な解決策を「自律的(能動的)」に導き出すという。

出典:日本経済新聞
1-1. AIエージェントが求められる理由
その理由についてソフトバンクのホームページでは次のように説明している。
「『AIエージェント』は多くの業界で革新的な変化をもたらす存在として期待されています」
その例として下記を挙げている。文章はそのままです。
- ヘルスケア業界:カルテの既往履歴や検査結果のデータを元に患者一人一人の症状を分析して、個人の症状に基づいたアドバイスを提供します。これにより、遠隔地や医師不足地域への適切な医療サービスの提供が期待されます。また、医療従事者の生産性向上や業務負担の軽減にも貢献し、医療現場の効率化を実現します。
- 教育分野:生徒に対しそれぞれに最適化された問題や解説を提供します。個々の理解度や進捗に合わせた学習支援が可能となり、学習効果を高めることが期待できます。さらに、教師に対しては授業計画や教材作成の支援を行い、教育現場の業務負担を軽減し教師不足の課題を解決します。
- サービス開発分野:(後述)
- 旅行やエンターテインメント業界:ユーザーの予算や好みに合わせた旅行プランや商品の購入をレコメンドしユーザー体験の向上や売上の向上に寄与します。
これらの業界に限らず、社会全体として人手不足や業務の複雑化が大きな課題となっているいま、AIエージェントの導入により、業務効率の向上やサービス品質の改善、CS満足度の向上が期待できるため、その活用は今後さらに広がっていくと考えられます。
- サービス開発分野の詳細説明には、次のような説明がある。
「ユーザーの要望に基づいて要件定義・設計を行い、その内容に沿って自動的にコーディングしてサービスを開発することが可能になります。デザイナーが不足しているチームにおいては、デザインやロゴの自動生成により、サービス開発のスピードと効率を大幅に向上させることが期待できます」
この説明は、どのような立場の人が誰に何を説明しているかまるで分らない。このような部分こそ、「オタク」が書いた部分と言え、本稿で私が読者に注意を喚起したい部分である。
この書き方では、どのような業種のサービス開発かわからない。広告業のようにも取れるが、確定できまない。この説明を書いた人は、きっとこの分野(AIとか広告)に詳しく、もし問い合わせれば「そんなことは言わずもがな」だと一蹴されてしまうかもしれない。
しかし、書き屋(ライター)の基本は、難しいことを中学生にもわかるように「翻訳」して書くことだ、と雑誌の記者修行時代に編集長に叩き込まれた。中学生にも、ということは義務教育修了者という意味だ。
ま、今後、いろいろな分野でのAIエージェントの活用が期待されている。
1-2. AIエージェントの課題
また、ソフトバンクでは、「AIエージェント」の活用には多くのメリットがありますが、以下の課題も存在します」と以下のように説明している。
- ハルシネーション:AIが実在しない情報を生成してしまうリスクがあります。重要な意思決定においては、AIの出力を人間が検証する仕組みが必要です。
【筆者註】ここでもいきなり『ハルシネーション』という言葉が飛び出す。長年、英語ビジネスの世界にいた筆者でも、はて、何のことだっけ、というほど稀に聞く英単語だ。これはhallucination(幻覚)が語源のAI業界用語だが、何の説明もなく唐突に出すのは書き屋の流儀ではない。これはオタクの書き方で、自分を高みにおいて読者を見下している感じがしないでもない。
- セキュリティとプライバシーの保護:機密情報や個人データを扱うため、情報漏えいや不正アクセスへの対策が不可欠です。データの暗号化やアクセス制限が求められます。
- 倫理的・法的な問題:AIの判断プロセスが不透明な場合、責任の所在が不明確になる恐れがあります。透明性の確保や倫理的なガイドラインの遵守が重要です。
- 専門分野の人材不足:AIエージェントを効果的に導入・運用するための専門知識を持った人材が不足しています。組織内での人材育成や外部専門家との連携が必要です。
2. オタクの弊害
2-1. 曲者は周りが見えないオタク
一番の興味は、どのようなビジネス人がこの「AIエージェント」システムを使っていくか、だ。
いろいろな業界のいろいろな分野に「オタク」(*)がいるが、この人種が曲者である。この人種は特定の分野には詳しいが、それ以外の周辺状況はあまり認識できていない。
(*)「オタク」とは、ある特定の分野や趣味に熱中し、詳しい知識を持つ人のことを指す。もともとは、アニメや漫画、コンピューター、ゲームなどのサブカルチャーに熱中する人を指す言葉として使われ始めたが、現在では、その対象は幅広く、PCソフト、鉄道、アイドル、歴史など、様々な分野にまで広がっている。「愛好家」、「マニア」、「ファン」、「熱烈な支持者」などともいえる。
「AIエージェント」の活用に当たっては、このような「オタク」に丸投げせず、経験があり見識の高いジェネラリストの監修が必須である。
「オタク」は、その分野においては圧倒的な知識と取り組み情熱を持っている。その点では全否定することはできない。むしろ、その知識をお借りしたいものだ。彼らの問題点は、ビジネス全体を展望する知見に欠けることだ。自分の直近の事象はよく見るが、それを含む全体像の把握力が弱い。

筆者がAIで生成した画像。「オタク」がAIで画像を生成しているところ。
2-2. オタクが作ったホームページ/アプリ
例えば仮に、新しいホームページやアプリに出会ったとする。
当方がその中で、目的のページ(C)へ速く到着したいとする。ワンクリックで(C)へ飛べると思うが、そのクリックボタンが見つからず(A)や(B)のページを経過しなければいけない。たしかに(C)を閲覧するには(A)や(B)の情報が必要だ。しかし、閲覧者は(A)や(B)の情報を、すでに承知している人もいる。そういう人たちは(A)や(B)のページをスキップして(C)へ直接行きたいのだ。
では、サイトマップでチェックすればいいではないか、と思う。しかし今度は、サイトマップがどこにあるかわからない。通常はフロントページの下とか、袖のどこかにすぐ見つかるのだが、それがなかなかわからないホームページやアプリがしばしばある。
「オタク」が作ったこのようなホームページやアプリは、見かけはきれいに仕上がっている。いろいろな新しい技術も盛り込まれている。しかし、それはきれいなだけで、実用的に便利ではないのだ。このようなホームページ/アプリは、制作者がコーディングのオタクで、楽しんで作っているように思える。あれもできる、これもできるというような新技術をテンコ盛りに駆使したものだ。見てくれは良いかもしれないが、実用的には非効率的だ。
ホームページやアプリを制作するときに、依頼者はいきなりその筋の「オタク」業者に発注していないか。自分たちよりその筋に詳しい「オタク」業者なら間違いないと思っていないか。これは大きな間違いだ。
2-3. 外注の基本
ホームページやアプリを制作するときにはまず、次のことを吟味しなくてはならない。
- ターゲット・グループ(1):つまり、誰がそのホームページやアプリを見るのか、活用するのか。
- ターゲット・グループ(2):そのグループのホームページやアプリを利用するときの技術力。
このようなことは、ホームページやアプリを制作するコーディング・オタク(製作者)は知る由もない。
発注者はコーディングなどは知らなくても、上記①や②についてはよく知っている。そのことを制作者に十分説明する必要がある。
コーディングができる(ホームページやアプリを制作できる)からと言って、ターゲット・グループを知っているとは限らないのだ。
2-4. ゼネラリストがAIオタクを使いこなせ
生成A Iの分野にも「オタク」は大勢いるに違いない。しかし、「オタク」はその壺の中のことは十分承知しているが、ビジネス全般やマーケティング全般をよく知っていたり、十分な経験があるわけではない。つまり、ビジネスのゼネラリストではないのだ。
そうした「オタク」さんたちは、生成A Iの分野でも、
「あれもできるぜ」
「こんなこともできます」
なんて言って、生成A Iを触ったこともない上司のゼネラリストにいい顔をしていたに違いない。
そんなところへ「AIエージェント」なるコンセプトが登場してきた。そういう分野が苦手なゼネラリストは、ますます引いてしまうだろうし、AIオタクはますます鼻を高くしそうだ。
ここはどうか、ゼネラリストたる立場の人が大所高所からその企業や部署の方針をしっかり出し、「オタク」を含む部下へ的確な指示を出し、部下はその中で「AIエージェント」を活用してほしいものだ。
3. 私のAI生成活用法
ご参考までに、私の生成A I活用法をご紹介したい。
私は傘寿を超えたとはいえ、日本文化を英語で世界に発信することをライフワークのようにしている。そのために日本の文化、風俗習慣などを英文で執筆し、電子書籍としてAmazon.com から世界に向けて発売しているし、ブログ『Masaato Blog』でも公開している。
英文の電子書籍は、すでに7冊、日本語では11冊も出版しているので、もう「作家」?かもしれない。
また、日本語ではfacebookやブログなどに日本語文を頻繁に投稿している。内容は海外にいる外国人の友達にもわかるような話題を投稿することもあるが、すべて日本語だ。最近ではインターネット上の文書は、瞬時に希望する言語へ無料で翻訳できるので、私の投稿は彼らにより彼らの母国語に瞬時に翻訳されるからだ。
私は以下のようにAIで文章の推敲や要約、英文化、および画像の生成などを行っている。
3-1. 使っているAI
最初からよく使っていたのは
3-2. ウェブ検索
以前はあることを調べようというときには、Googleなどの検索機能を使っていた。
ググると、関連記事が検索ロボットによって列挙される。その中から自分の疑問の答えに近いものをいちいち開いてチェックしなければならなかった。
しかし、AIになってからは、自分の質問に対してだけ、詳しい回答をその場でタイピングしているかのようにPCの画面に打ち出してくる。最初は本当に感激すらした。
今ではこの検索機能を1日に何回も上記3つのAIで活用している。
3-3. 日本文の要約
お他人さんの文章でも自分の文章でも、3,000字とか4,000字くらいの長い日本文を500字とか800字に要約するときに便利だ。時間も1分もかからない。上記の複数の生成AIを使って、出来上がった要約を比較検討し、それを自分でさらに、自分の主張したいところが漏れないように編集する。
要約を任せっぱなしにすると、全体をうまく、指定文字内にまとめてくれるが、自分が力説したい部分が平準化されてしまうこともある。
3-4. 英文の推敲
自分で書いた英文を、以前は知り合いの外国人に推敲してもらっていたが、実のところ、彼の英語力がどのくらいかちょっとわからなかった。ま、自分より良いだろう、ネイティブだし、くらいにしか思っていなかった。
しかし、ChatGPTを使ってみて、天地がひっくり返るほどビックリした。人間の先生に赤を入れられたように、訂正した部分を、「ここのところはXXXXという動詞を使いZZZZZZZ,ZZZZZ」と表現する方がフォーマルです、とかカジュアルです、と指摘してくれる。英作文の添削を生身の先生から指導を受けているようだ。
3-5. 英文作成
時間のない時に、日本語をそのまま、
「次の日本語を英文にしてください」
と、指示し、当該日本文をコピペしても、そこへ書いても、即座に英文にしてくれる。
その英文を検討すると、自分ではしたことがないような発想の英文だったり、動詞の使い方をするので、これも大変勉強になる。その方が自然な表現だと思うことがしばしばある。
いずれにしても、このような翻訳ツールがあれば、英語ができない人でも本当に便利だね、と言いたいところだが、そうはいかない。文章に出てくる人物が男性か女性か取り違えることもあり、heとsheを間違えていることがある。
また、ある段落の翻訳英文が、どうも私の期待した英文になっていないこともあった。自分の日本文を読み返したら、その日本文がおかしいこともあった。翻訳ツールは正直なのだ。
やはり、英作文や英文読解がある程度できないといけない。
3-6. 英文和訳
英文はネイティブほどではないが、結構平気で読める。しかし、その段落中の単語はすべてわかっていても、意味が解らないことがしばしばある。そんな場合は、その部分を英文和訳機能にコピペしてかけると、霧が晴れるように見事な日本語になってくれる。
また、長い英文を自分で読み進めるとどうしても時間がかかるので、全文を英文和訳機能にかけると時間短縮になって便利だ。
3-7. 日本文作成
この機能は日常的にほとんど使ったことはないが、次のようなことができる。
- 日本文の創作:あらすじを入力し、〇〇〇〇字くらいの恋愛小説を書いて、と指示すると本当に小説を書いてくれる。これは試してみた。
- 聞き取りで文章起し:自分の書きたい内容を、スマホのマイクで話して文字化することは、誰でもできることだが、これを日本語で〇〇〇字くらいでまとめてくれ、と指示を出すと、正しい日本語の文章にしてくれる。冗長な話し言葉が、ちゃんとした日本語の文章に、しかも指定した文字数でまとめてくれるのだ。
最近、文学賞をとった新人作家は、受賞作の一部分をAIで生成したと「告白」している。
私は、書き屋としてこの方法をとることは沽券に関わるという観念が抜けないので、まだ使ったことがない。
3-8. 見出しの作成
もう一つ凄いのは、英文や日本文の見出しを作成できることだ。
英文や日本文を他から持ってきてコピペし、「見出しを2行で作って」とか「見出しを3行で作って」と指示すると、たちどころに作成してくれる。
英文和訳や和文英訳をさせたときにも、同時に見出しを作成するように指示すると、見出し付きの文章が出来上がる。
3-9. 画像生成
3-9-1. 実例1. 自分のアイコン
この作業は結構楽しい。現在、facebookのアイコンなどに使っている自分のプロフィールの画像を作った時の様子を順を追ってご紹介しよう。
- まず画像生成A Iに「この写真をもとにアニメ風のキャラクターを作って」と自分の写真をアップする。
- すると下のような画像が生成される。最初の画像。
- AIのコメント:
「できました!この写真をもとに、アニメスタイルのキャラクターを描き出してみました。どうぞご覧ください。気になるところや、別の雰囲気で作り直したい部分があれば、どんどん教えてくださいね」
かなり、年寄臭いので(実際の私より全然若く見えるけど)「もっと若く」とか、背景や洋服の色などに修正を何回か入れ、「Masato」の文字を胸元に、少し右上がりに配置して、眼鏡もかけさせて最終的な画像までもっていった。眼鏡の色と洋服の色も統一させた。 - AIのコメント:
「できました!ポップな書体で「Masato」の文字を胸元に、少し右上がりに配置して、軽やかでリズミカルな印象に仕上げています🎨💫他にも入れてみたい文字や、配色の変更、小物の追加などがあればぜひ教えてくださいね。一緒にどんどん磨き上げていきましょう!」


3-9-2. 実例2. 男の同性愛者
これはfacebookで同性婚について投稿したときに作ったものだ。
初めに「男の同性婚の風景」と指示したら、若い男性のカップルの写真だったので、年齢を上げたり、洋服の指示をしたり、背景を変えたり、牧師を追加して以下のような画像にした。

3-9-3. 注意
画像生成の場合は、最初に列挙した3つの生成AIに同じ指示を出し、出てきた最初の画像を比較し、自分のイメージに近いものを修正していくようにしている。
このように私は、現在の自分の仕事の中で、この歳(80歳)にしては結構積極的に生成A Iを活用している。しかし、仕事自体がもはや、お他人さんと絡んでするものではないので、この「AIエージェント」は私にはそんなに関りをもって来ないかもしれないが、その成り行きには興味津々たるものがある。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。