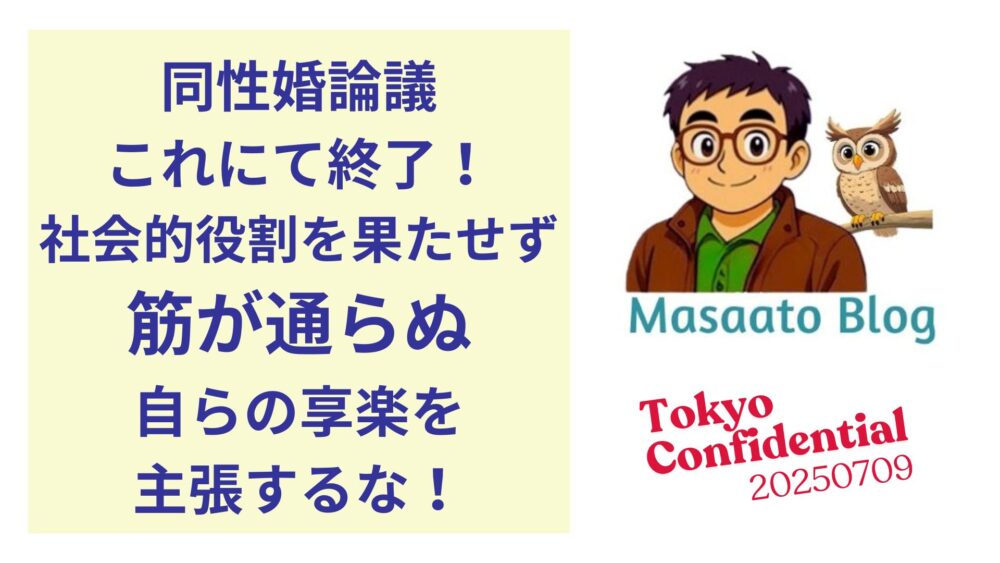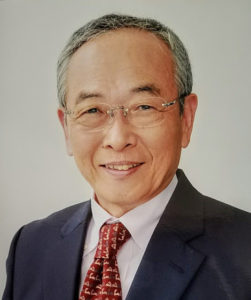【contents】
1. 両性とは、憲法成立時から現在に至るまで「男」と「女」のこと
「レスビアンやゲイなど同性にのみ惹かれる性的嗜好を持つもの同士が結婚できないのは、それを禁じている民法などの規定が憲法14条(法の下の平等)に違反する」
やや旧聞になるが2021年、札幌地裁では、このような判決を下した。

私はこれにかかわった裁判官たちは、学生のころから法律ばかり勉強してきて、世の中とか社会の仕組みについて、ほぼほぼ知らないのではないかと思う。「法律馬鹿」と呼ばれることもある。
日本国憲法第24条では、「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない」と規定されている。
この「両性」という文言は、憲法成立時から現在に至るまで「男」と「女」を指すものと解釈されている。同性間の同棲は「婚姻」とも「結婚」とも言わない。
2. 裁判官はダイバーシティに安易に感化
しかし近年、無教養な(世間やモノを知らないという意味)憲法学者の間では、この「両性」が男女を限定するものではなく、あらゆる性別の組み合わせを許容するものとして解釈することも可能であるという、荒唐無稽なことを言っている。
いまはやりのダイバーシティ(多様性受容)の傾向に安易に感化されている。「婚姻」とか「結婚」が何であるかも、辞書を引くところから始めよ、と言いたい。
3. 婚姻には社会的役割あり
婚姻とは、女性と男が一緒に暮らして仲良くし、できれば子宝に恵まれ、自分たちの幸福の享受ももちろんのこと、次世代の人材を育成するという社会的役割がある。
レスビアンやゲイの「同棲」は自由だが、子供は絶対にできない。養子の話は論外である。
子作りや次世代人材の育成という社会的役割も果たせず、ただひたすら自分たちの快楽の「同棲」を、普通の「結婚」並みに認め、普通に結婚したものが享受している社会的利点を自分たちにも、というのは、あまりにも自分勝手ではないか。その社会的利益には、正常な結婚者や結婚予定者の税金も使われるのだ。
4. 受益者負担で独立せよ 健常者の税金を当てにするな
もし、そのような利益を享受したいなら、「受益者負担の原則」に従い、自分たちで自分たちだけのための共助組合などを作って独立していくのがいいだろう。健常者の税金をあてにするような要求をすべきではない。
というと、「筆者には少数者保護の精神がないのか」というような頓珍漢な非難も出るかもしれない。そんなことより、そんな頓珍漢な非難が浮かぶ自分に疑問を持つべきだろう。
問題は、世の中には、筋が通ることと通らぬことがある、ということだ。
画像はAI作成。