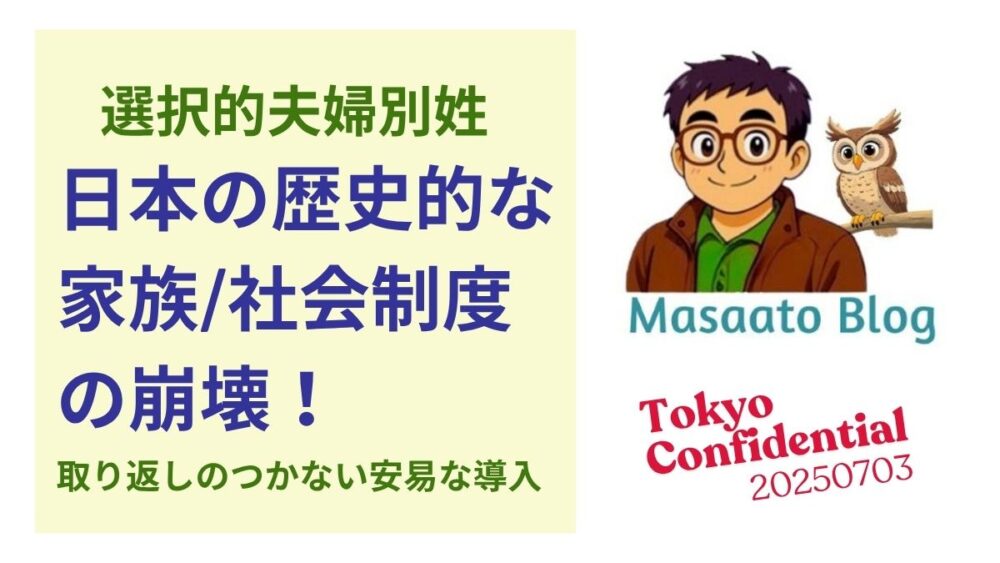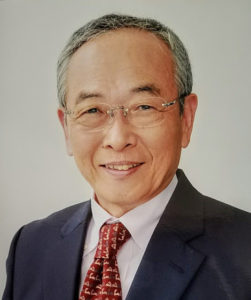【contents】
1. 取り返しがつかない安易な導入
いま喧(かまびす)しく議論されている選択的夫婦別姓。これを軽々に導入することは、日本古来の家族という国家運営単位を崩壊させることになる。いったん取り入れたら、これを復元することは極めて難しい。
この論議は、日本の社会問題解決のために日本から発生したものではなく、海外発生の事案に、軽薄なリベラル・似非フェミニストが飛びつき、時流に乗ってきていることを十分自覚すべきである。

例えば仮に選択的夫婦別姓が導入されたとすると、次のようなことが発生する。
1)若い山田家が夫婦別姓で、父親が山田姓、母親が佐藤姓になったとする。生まれてくる子供の姓はどちらかにしなければならないから、父親、または母親とは違う姓になる。
2)生まれてくる子供の姓は、子供が何人生まれようと、生まれる前に一律に父親姓(山田)か母親姓((佐藤)に決めることができる。
3)子供が生まれ出生届を出す都度、姓を決めることができる。つまり、兄弟姉妹の姓が違うことがある、全員同じこともある。
要するに姓は、古来から日本が馴染んできた「家族」という単位の呼称ではなく、家族一人一人の個人姓へと抜本的な変貌を遂げてしまうのだ。父母がいて子供がいる家族を呼ぶ名前がなくなり、自分の姓を持っている大人の男女二人と別々の姓を持った子供何人かが共同で暮らす、名前のない集団が出来上がるのだ。
日本古来の風俗習慣がなりたたない社会へと変貌する。
1-1. 「山田さんチの子」とは、もう呼べない
選択的夫婦別姓を導入すると、次のようなことが出てくる。
- 「山田さんチのお子さんて、お行儀がよろしいわね」とはもはや言えない。以前の山田家には、山田姓の子供と佐藤姓の子供がおり、”山田さんチの子供”としては、家族単位としては何もないから。
- もと山田家の家族は、家族ゲームや行楽、外食など、何かと山田姓と佐藤姓に分かれて別行動になりがちである。対抗意識も出てこよう。
- どちらかの親が亡くなったとする。以前なら、「お母さん(あるいはお父さん)が亡くなっても、みんなで頑張ろうよ」といって、家族の固い絆で頑張れた。しかし、選択的夫婦別姓となれば、そうなならない可能性も出てくる。
- 一番問題なのは、子供たちである。「なんでボクとネエちゃんは姓が違うの」と不思議に思うだろう。仲良く手をつないで歩くのもはばかられる。子供が疎外感を感じるようになる。
この制度で一番の犠牲者は、何も意見を言えない子供たちである。母親の都合で、このような子供への一番のしわ寄せ、家族分解が起こってもいいのか。
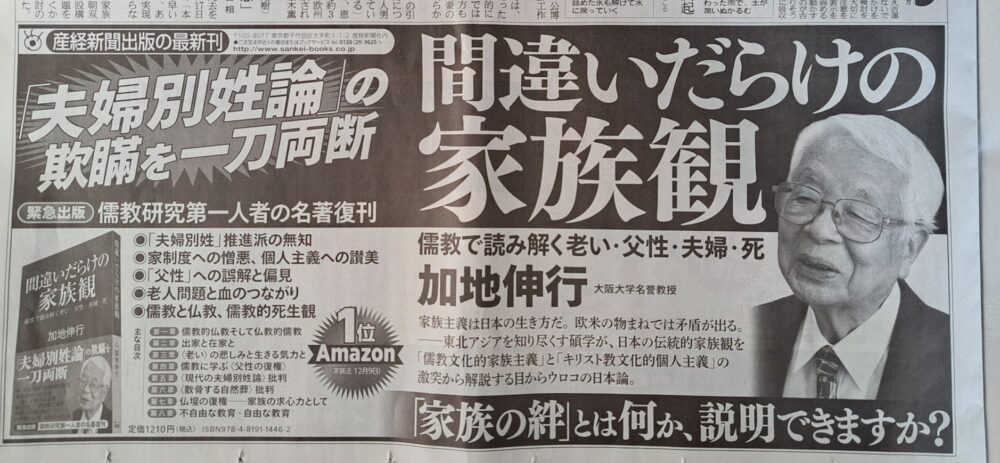
2. 世界で最長歴史の日本
世界には日本が国として認めている国が196ヵ国ある。そのうち、国連に加盟しているのは193ヵ国。また、そのうち歴史が最も長い国は、わが国・日本で、2025年で建国2681年を迎える。
日本は紀元前660年に神武天皇が国を創って以来、その後王朝が一度も滅びることなく続いている。
日本に次いで、2位はデンマークで1086年、3位はイギリスで956年と長い歴史を持っている。とはいえ、日本の半分にも及ばない。
建国以来今日まで日本は、女性虐待や奴隷制度など人権にからむ大きな問題もなく、西欧のような個人中心ではなく、家族を中心とした安定した国家を運営してきた。
そういう仕組みが日本人の精神風土に適合していたため、いくつかの日本人同士の争いはあったものの、諸外国の例に見るように国家が分裂することもなく今日まで続いて来ている。
しかし開発途上の諸外国では、日本では考えられないような女性の人権が無視され続いている国家が、いまなお、いくつもある。
こうした状況に鑑み国連では、女性の人権と平等を保障するための国際条約「女性差別撤廃条約」(*)を1979年に採択し、1981年から発効した。日本は1985年に批准した。
(*)正式名称:「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約]
英語名:Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, 略称:CEDAW
3. 2700年も続く家族中心の日本
世界で最長の歴史を誇る日本では、諸事万端、以下のように家族が中心で行われている。
- 日本では姓(名字、または苗字)は個人のものではなく「家の名」であった。武士や農民でも、家ごとに家紋(家の紋章)が定められ、個人の象徴というより家の独自性を表していた。
- 職業の世襲と家業。江戸時代には、職業が家単位で継承されるのが一般的であった。商家、農家、職人などは、技能や地位を「家」に属するものとし、子孫に伝えてきた。
- 家督相続。「家を継ぐ」という考えが強く、長男が後継者とされることが多くあった。後継者がいない場合には婿養子を迎えることで「家の断絶」を防ごうとした。
- 葬儀・墓文化。日本の葬儀や供養の文化は家単位。多くの家には「先祖代々の墓」あり、個人の死後は家のお墓に入るという意識が強い。西洋のように個人で一つ一つの墓を建てない。
- 仏壇での供養。「家の仏壇」で行い、子孫が先祖を祀るのが一般的。
- 結婚。女性が男性の家に入り、「家の名字を名乗る」のが通例である。結婚式や披露宴も〇〇家と▽▽家で客を呼ぶのが普通であった。
選択的夫婦別姓で家族が無くなれば、このような日本の社会的仕組みは雲散霧消してしまう。2000年以上もかけて丁寧に構築され、若干の改定はあるものの、今なおそのなかで生活している社会習慣を、一時の思い付きで買えてしまっていいものか。
4. 選択的夫婦別姓の浮上
選択的夫婦別姓問題は、もとはといえば先に述べたように国連で1979年に、女性の人権と平等を保障するための国際条約「女性差別撤廃条約」を採択し、1981年から発効したことに発する。日本は1985年に批准した。
最近ではマスコミをにぎわすようになったのは、経団連が2024年6月に、政府にこれを推進するよう提言したのが端緒である。
女性の社会進出に伴い、結婚して改姓することで仕事や実績、学歴証明、SNSの名前などの使用が不便になる。そこで「職場での婚前旧姓使用の継続性」を求める声が高まっている、と政府に迫った。
しかし、そのような不便がどれほど高まっていたのか、数値としてどのくらい出ていたかは不明である。またなぜ今頃、突然思い出したように政府に迫ったのか。根拠に乏しいといわれる所以である。
また、経団連がその理由として挙げたビジネス上の課題の多くは、実際には解消済みだと自民党の会合で指摘された。その会合に出席していた経団連の永井浩二副会長もそれを認めた。
これで、この一件は落着したのだが、現在では、与野党の夫婦別姓推進派に政治目的として利用され、別方向に動いている。
4-1. 選択的夫婦別姓の方法
選択的夫婦別姓とは、女性が結婚した時に夫の姓にしないで、自分の姓をそのまま戸籍登記することができる方法である。もちろん、日本のこれまでの慣習のように夫の姓で登記しても良い。だから「選択的」という。
4-2. 子供の姓の決め方
その場合、生まれた子供の姓をどうするか、という課題が出る。
子供の姓の決め方には2つの方法がある。
1)生まれる前に父親の姓か母親の姓かを夫婦が決めておく。きょうだいは全員同じ姓となる。決めないと婚姻届けは受理されない。
2)生まれる都度、どちらの姓(母親の姓または父親の姓)かを決める。きょうだいの姓はバラバラとなる。生まれた子供の姓が決まらないと、現在の戸籍法では、生後14日以内に出生届を出さなければならないので、出生届は受理されず子供は無戸籍となる。立憲民主党、共産党、公明党がこの説を主張。
5. 日本の家族・社会制度を崩壊させる大問題点
前記のように親が夫婦別姓を選択した場合、子供は必然的に1)でも2)の方法でも片親とは別姓となる。2)の方法だと、きょうだいとも別姓となるかもしれない。
つまり、長子は父親姓、第2子は母親姓となると、きょうだいは別姓となる。きょうだいの一人は、どちらかの親とも別姓である。
きょうだいを仲良くなるように育てても、子供としてはどうして自分たちは、親やきょうだいと別姓なのかと、必ずや疎外感を味わうときがくる。
母親が自分の都合を通したばっかりに、子供にしわ寄せが行くのだ。
日本から家族全体を呼ぶ名前が無くなるのだ。つまり「家族の姓」というものがなくなるのである。共通の姓が存在しない家族とも呼べない、共同生活集団が生まれるのだ。
個人に姓はあるが、それは家族をまとめる絆の役割は果たさない。先祖から子孫へと世代を重ねてきた、そしてこれから続けられていく家庭の呼称を否定するものだ。家族の一体感は薄まる。
家族の「戸」籍はなくなり個人の「個」籍がのこるのみ、つまり家族の解体を意味する。これまで2,600年以上もの長きにわたって営々と育まれてきた日本の家族制度や社会制度の破壊につながる、とてつもなく大きな課題なのである。
6. 「旧姓の通称使用」で問題は解決可能
何も、日本古来の家族や社会制度を破壊するような選択的夫婦別姓制度を導入しなくても、女性が旧姓をそのまま使える「旧姓の通称使用」という方法がある。マイナンバーカードや、住民票・印鑑登録、運転免許証、健康保険証、銀行口座、そして職場での名刺・メールアドレスには、一律な方法ではないが、旧姓を併記できるので選択的夫婦別姓制度を導入うる必要はなくなる。
自民党の高市早苗元総務大臣は、選択的夫婦別姓の導入に強く反対しており、同制度へ反対する自民党内の議員連盟「『絆』を紡ぐ会」の共同代表を2021年時点で務めた。
現行の夫婦同姓に賛同し、「家族の一体感を守るためにも夫婦親子同姓を堅持すべき」、「日本には日本の制度がある」と2021年に語っている。姓が結婚に伴って変更されることによる不利益に関しては、「旧姓を通称(通名)として使用できる場面を拡大すればよい」と主張している。
自民党はこうした実情を経団連に説明した。こうすれば、子供たちに無用な疎外感や家族の結束感の欠如を迫る必要はなくなる。
こうしてみてくると選択的夫婦別姓の仕組みは、子供からの視点に欠ける。導入論者は妻や夫のことばかりにかかわり、親よりも存在感が弱く発言もできない子供を軽視している。
既婚女性が仕事をしやすくするためには、こどもの立場を無視していいのか。日本に代々受け継がれてきた、夫婦同姓の家族を社会の最小単位としてきた社会を、その時代の一時の都合で安易に変更していいのか。
日本が世界に誇れる豊かな同族的感性、家族愛、家族への帰属意識などを崩壊させてしまっていいのか。いったん崩壊すれば容易に再構築できないものへの恐れを認識すべきではないか。
7. 推進派の無教養
推進派の立憲民主党の野田党首は、夫婦同一性は日本古来の伝統ではなく、まだ明治時代に始まったばかりのものだ、遵守するに能わず的なことを嘘ぶいている。明治31年に制定された民法のことを言っているのだろう。
これこそ無教養といわずして何といおう。
日本では、江戸時代から多くの庶民は夫婦同姓であった。庶民は名字は持たなかったというのは事実ではなく、名字はあったが幕府が「身分秩序」を守るためと、武士と庶民を明確に分ける必要があったので、庶民は姓を公称ができなかったとされるだけである。歴史的古文書などがそれを裏付ける資料がでている。
推進派の思惑は、最近、喧しくなってきているダイバーシティ(多様性)への迎合のように見える。女性が自立して仕事ができるよう、わが党はいち早く女性が仕事をしやすく配慮している、と言いたげである。女性へすり寄り、票稼ぎの意図が丸見えで下品だ。
8. 男女格差世界118位は非実態
彼らには、日本は外国から遅れている、という無教養な先入観がある。例えば、スイスのシンクタンク『世界経済フォーラム(WEF)』が148ヵ国の男女平等度を順位付けした『男女格差(ジェンダー・ギャップ)報告』などで、日本がことし(2025年)118位だったという報告が出ると、外国かぶれの輩は、アプリオリに(盲目的に)女性の地位向上、管理職の増員などということを口走る。
118位のどこがいけないのか。
この順位は、例えば内閣の女性大臣の人数とか、企業の女性管理職に占める女性の割合とかの、単に数値比較であり、その国独自の歴史や風土、習慣などは吟味していない。
日本を118位と位置付けたWEFの数字は、そういう類の数値比較ならそうかもしれない。しかし、日本の女性が上から数えて118番目というほど、社会や職場で激しい差別や虐待を受け、多くの優秀な女性が、女性が優遇されている海外へ流出しているのか。
男女格差という点で日本は118位でも、戦後の驚異的復興はできているではないか。GDPだって世界でトップクラスだし、その陰で日本の多くの女性が毎日泣いているというのか。男たちの実力や努力はどのように評価しているのか。
WEFのみならず、国連の女性差別撤廃委員会でも日本に対して選択的夫婦別姓制度の法制化を勧告するなどしている。
8-1. 全女性の底上げではなく、優秀な女性の登用
日本では、女性を平等に扱ってこなかった、だから西欧並みに女性に働く機会を、というのは当然のことだ。しかし、間違ってはいけないのは、女性全員の立場を持ち上げ、例えば国会議員の数を男女同数にするとかのような数合わせをすべきではない、ということだ。
そんなことをすれば、優秀な男が男女の数合わせで泣きを見ることも出てくる。男女同数の国会議員数ならば、GDPは下がるかもしれないし、日本の今日の繁栄は達成できなかったかもしれない。日本には、日本の男女の役割があり、女性は太古から「家族の太陽として」陰ながら男を支えてきて今日の日本があるのだ。
しかし、時代が変わり、女性も男並みに働きたいというなら何の異論もない。母性という女性の特性を両性で保護しながら、彼女らの素晴らしさを生かせていけたら良い。男にはない良いものを持っているかもしれない。それには、女性全体の立場を一律に底上げするのではなくて、男女混合のなかでも男にも劣らず素晴らしい女性を、男並みに伍せばよいということだ。
そこを履き違えて、男女の員数合わせに血道をあげるのは愚の骨頂といえる。
8-2. 国連は左翼の巣窟
国連の事務局は「左翼の巣窟」であるとよく言われる。日本の反日左翼NGOは40年以上にもわたり国連でロビー活動を繰り広げ、国連の委員たちに虚偽の情報を吹き込んで、日本がいかに人権侵害を行っているひどい国であるかを信じ込ませてきた。従軍慰安婦問題などもその最たるものである。
それを信じる方も情けない。自らの検証活動をまるでしていない。
たとえば、従軍慰安婦問題の中では、日本軍が韓国女性を「sex slave(姓の奴隷)」のごとく扱った、と言われているが、この言葉を国連に広めたのは、英語圏の人ではなく、なんと日本人なのである。
この案件については、別途、論考する。
9. 補足:欧米文化・制度への憧れ
英語で読み書き、発話ができるようになると、「個人を中心とした」英語圏での生活方法や文化、制度などにつき、いろいろなことを知ることとなり、「家・家族を中心とした”」日本に生きてきた者としては、それに感心したり、憧れたりするようになる。
それは自然なことで、なんら異を唱える気はない。
しかし、1945年という終戦の年に生まれた世代としては、本人の努力ではなく、実家の財力で学生時代に英語圏へ留学したり、そのまま現地の企業へ就職、その後帰国して、英会話力を武器に高給職種についている輩の中には、アプリオリに(盲目的に、経験や事実の検証なしに)欧米風を賛美する者がいるのは、誠に遺憾なことだ。
そういう輩は、えてして英会話能力という下駄を外せば凡人以下の才覚しかないものだ。英会話の質も良いとは言えないことが多い。英文読解や英作文能力も英会話能力とは、別物と思うようにしている。
英語を話せない日本人は、英語を話せる日本人はすごいと思うが、それは危険な認識だ。英語を話せる日本人でも、その英語がピンキリであることを知るべきだ。英語をペラペラしゃべる輩でも、その英語の質が良くない輩はたくさんいるのだ。
私がよく同席した外人さんは、ビジネス会議の席上、英語を流暢に話している日本人について「彼女(彼)の日本語の品質はどうか?」と聞いてくことが何回かあった。
英会話は通じても、しっかりした母国語が話せるかどうかは、その人物の人品骨柄や教養の見極めができるからだ。けだし慧眼といえる。
これからの国際時代に備えて、小学校から英語教育をしていくという考えがあり、現に実行している教育委員会もある。しかし、大人になって仕事につき、英会話ができても、たとえば著名な短歌の十種も朗詠でいないようでは、日本人の日本人たる素養がないことになる。
そんな人間に、日本のことを外国人に説明してもらっては困るのだ。日本の文化、歴史などを十分に正確に理解できてこそ初めて外国人と対応できよう。
英語より先に学び、身に着けることがあることを承知しておくべきだ。
10. まとめ
選択的夫婦別姓制度の導入は、以下のような問題を孕み、日本の家族制度や社会制度を破壊するので、導入すべきではない。女性が旧姓をそのまま使える「旧姓の通称使用」という方法で、働く女性の不都合は解消されている。
- 本制度は、結婚しても働き続けたい女性のためのもので、生まれた子供は片親や兄弟姉妹と姓が異なることが発生することがある。家族としての名前はなくなり、家族としての結束感も薄れる。子供は片親や兄弟姉妹と、これまでの日本の家族のように温かいものを感じられなくなる。家族相互に疎外感を感じるようになる。
「ひとりの親」の勝手で、「何人もの子供」が温かい家族の中で暮らせなくなってもいいのか。子供の意見はどこに反映されるのか。 - 本制度の導入により、日本古来からの風俗、習慣などは維持されにくくなる。
例えば、お墓の名前はどうするのか。また、例えば、以前に「山田さんチ」と呼んでいた家族が本制度を導入した場合、その家族は何と読んだらいいのか? つまり家族の呼び名が無くなったので。 - 家督相続はどうなるのか?父親の姓を待つ子供だけが相続するのか?父親の姓を名乗らない子供に、父親は相続をする気になるのか?
- たった一人の母親のために、複数の子供は疎外感を持ち、家族の概念はなくなり、それぞれが一個人に帰してしまうという、日本古来からの家族制度や社会制度をひっくり返してまで、本制度を導入すべきではない。
- 女性が旧姓をそのまま使える「旧姓の通称使用」という方法で、働く女性の不都合は解消されている。
以上です。最後までお読みいただき、ありがとうございました。