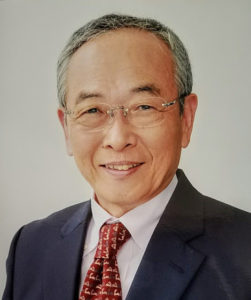令和の昨今、日本のあっちこっちで「事件だ!事件だ!」。奇妙なこと、不思議なこと、バカバカしいこと、いってい、何が起こってんだい? そんな「事件」に野次馬的に首を突っ込み、都々逸風にまとめ、その背景を探ってみる「野次馬的都々逸もどき」。自分のfacebook 「新津Masato」にすでに掲載済のものを編集してご紹介します。
【contents】
67 定員割れで大学ガラガラ 入った学生 脳内カラカラ
♬ハァ、これからどうなるの? どうなるの?

【画像出典】Youtube コバショーの受験最前線。画像中の「BF大学」とはボーダーフリー大学のことで、受験生が少ないなどの理由で明確な合格基準が設定できない大学のこと。
今年度(2025)、全国の私立大学の半数が定員割れとなったことが分かった。日本私立学校振興・共済事業団のまとめによると、入学者が定員に満たない定員割れとなった大学は、全国594の私立大学のうち53.2%に当たる316校に上った。
少子化の影響が大きいらしいが、喜んで良いのやら悪いのやら。つまるところ、贅沢言わなければなんとか大学に入れる、ということだ。学生が来なければ、私立大学も企業なので経営は成り立たない。
かと言っても、学力に関係なく全員を入学させるというわけにも行かず、一定の学力レベルに届かないと入学できないようにしている大学もある。
何はともあれ、大して勉強しなくても入学でき、入ってみれば学生数はすくなくて、教室も食堂もガラガラ、学生は大した勉強もしていないので、頭の中はカラカラと言うことかねぇ。
大むかし、英単語は8,000語以上とか必要ということで、旺文社の赤い豆単で夢中で覚えたころが懐かしい。確か、大学入学では応募倍率22倍、受験倍率13倍だったような気がする。
こういう時期だから、受験勉強をする代わりに読書だけは、まぶたがピクピク痙攣するほどたくさんして欲しいモンですな。
66 スマホの使用 2時間制限 スマホの洗脳 から解放
♬ハァ、良かったね、良かったね。
愛知県豊明市でスマートフォンの利用を1日2時間以内とする条例が、22日の市議会で成立した。子どもの長時間使用を心配してのことらしい。条例は10月1日に施行される。

【写真出典】日本経済新聞
ま、遅きに逸した感は否めない。子どもが長時間使用しての健康上の問題を懸念しているようだが、筆者はそれもさることながら、子どもが情報を「受動的」に受け続けること、また、その情報の真贋や信憑性などを子どもが判断できずに、人格なきスマホに「洗脳」され続けていることを大いに心配している。
私ら子供のころは、テレビすらなかったので、肥後守で物を作ったり、雑木林の中に「秘密基地」を作ったり、カスミ網を仕掛けたり、と毎日はそれなりに「多忙」であった。しかし、いまの子どもたちよりはるかに創造的な生活をしていた。
AI が発達して何かと便利になるだろうが、AI を使うのは人間だ。スマホに「洗脳」された子は、結局はAI などは使えず、本当にAI に使われる子が大部分になるのではなかろうかと杞憂している。
この条例には、罰則などはないが、子どもたちがスマホ離れする機会の嚆矢となることを期待する。
65 スマホ、スマホと騒ぐな子ども そのスマホは親のもの
♬ハァ、ほんとだよ、ほんとだよ。
これは私の発想ではなくて恐縮です。

【画像出典】トーンモバイル
親は、スマホを子どもに使わせるときに、その所有権をはっきりさせ、子どもにその使用時間を守らせるという約束事。たぶんカーラジオで聞いた。
つまり、
「このスマホはお母さんのものです。なぜならこのスマホの値段は高く、あなたの使用料もお母さんが払うからです。だから、スマホは〇〇時になったら、必ず私に返してください。それでよければこのスマホをあなたに貸してあげます」
という話だった。
つまり、スマホは、子どもに「買い与える」のではなく、親の所有権を明確にし、使用時間を守らせる、というものです。
64 何でもかんでも 1コ、2コ、3コ 、ヒトもそうして 数えるの?
♬ハァ、困ったモンだ、困ったモンだ。
TVで未就学児に、自分で自分の洋服(デザインや色)を選ばせる番組を見た。UNIQLOの店舗での収録であった。いつも、母親が選んだものばかり着ていたが、子供たちが選んだ洋服を見て、母親たちは自分の好みと違う洋服もあって、驚いていた。

画像は、AI Copilot で生成した。
それはともかく。驚いたのは、母親が洋服を数えるのに「1コ、2コ」と数えていたことだ。
そういえば、いまの若い人は何を数えるにも「1コ、2コ」だな。
「あ、彼は私より3コ上よ」ってな具合だ。
年齢にしろ、魚だって、肉だって、靴も皿も、なんでも「1コ、2コ」と数える。
これじゃあ、発展途上国の原住民とほぼほぼ同レベルだな。
「数助詞」の存在を知らないのかもしれない。
日本には、ものを数えるときには、そのものに独特の数を表す数助詞というものをつける。
ウサギは1羽(わ)、2羽、イカは1杯、2杯、履物は1足、2足、そしてタンスは1棹(さお)、2棹と言うがごとしだ。約500種類あるという。子供のころ、この呼び方に出会って、夢中で調べまくった思い出がある。
これらは数助詞といい中国由来のもの。中には握り寿司を数える貫(かん)というのもあるが、これは和製である。筆者も全部知っているわけではないが、本稿を書くにあたって、ざっと眺めていたら、蝶は頭(とう)で数えるらしい。数助詞にはいろいろと意味があって面白い。
中国ではなぜ、こんな面倒?なことを考え出したかというと、中国語の特性によるらしい。例えば英語ではbookの複数はbooksでsをつければわかりやすいが、中国語では本sというわけにはいかない。そんなところが数助詞の発生の元らしい。
数助詞500をすべて覚えよ、とは言わないが、日常的に使う数助詞くらいは覚えておいて使える方が知的生活が送れると思うが、いかがなモンかな。
間違っても、人を数えるときに「1コ、2コ」なんて数えないで欲しモンだね(笑)。