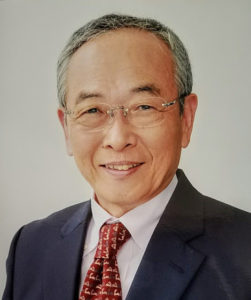日光に中禅寺湖ができたころ、赤城山の女神と男体山の男神が、それぞれ大蛇(オロチ)と百足(ムカデ)になって、その領有権を争った。その結果、敗れた女神はいくつもの山を越えて、とある山村へ辿り着いた。傷ついた女神は、身に刺さっていた矢で温泉を掘り当てた。また、女神の化身である大蛇を祭る「大蛇祭り」が毎年、盛大に行われている。祭神の大蛇は2tで全長108.22m、ギネスの世界記録に登録されている。
老神温泉には、そうした故事が語り伝えられている。
日光の戦場ヶ原へは何回も訪れている。しかし迂闊にも、どのような戦いが行なわれた戦場ヶ原なのか、この度、老神温泉で老体を癒すまで神話とはいえ知らなかった。出身が日光国立公園のある栃木県の家内からは、
「えっ? 知らないの?」
と、軽い侮蔑の視線が飛んできた。インバウンドの観光ガイド(全国通訳案内士)としては情けない。
【contents】
1. 戦場ヶ原の神話
むかしむかし、日光の二荒山(ふたらさん、現・男体山)に男神がいた。現在の二荒山神社(日光東照宮の隣)の祭神である。その姿は堂々とした大男で、山と湖を守る力強き神であった。
少し離れた現・群馬県には赤城山の女神がいた。凛として美しく、しかも強き力を持ち、人々に豊かな水と恵みをもたらしていた。
ある日、日光の高地に新たな湖が生まれた。今の中禅寺湖である。
その澄んだ水と神々しい景観を見たとき、二荒山の神も、赤城山の神も、こう思った。
「この湖は、わが領地にふさわしい」――と。
こうして、神と神との間に争いが起きた。
男体山の神は百足(ムカデ)の姿に身を変え、
赤城山の神は巨大な大蛇(オロチ)となり、
互いのしもべである獣や鳥たちを率いて、湖をはさんで睨み合った。
その戦いの舞台となったのが、今の戦場ヶ原である。
空は裂け、大地は揺れ、雷鳴とともに神々の力がぶつかり合う。
長き壮絶な戦いの末、ついに男体山の神が勝利し、中禅寺湖を自分の領地とした。
敗れた赤城山の神は、悔しさに耐えながらもその場を離れ、幾重もの山を越えて、今の群馬県・沼田の山奥・老神へと逃れてきた。
そこで自分の身に刺さっていた矢を抜き、地面を掘ったら温泉が湧きでてきた。その温泉の湯で、女神はその傷を癒やしたという。この温泉の湧きだした日が5月7日で、なんと筆者の誕生日である。
2. 老神という地名に2つの説
ひとつはその女「神」が年「老いる」までそこで静かに療養して暮らした、という説。人々は今もなお「追われた神が静かに眠る聖地」として語り継いでいる。
もうひとつは、女神の傷が癒えたころ、男神がようやく女神の隠れ場所を突き止め、再び攻め入ってきた。ところが今度は女神の方が強く、男「神」を「追い(老い)やった」ので、老神という地名になったという説である。
なお、日光側の伝説では二荒山の男神は大蛇として、また、赤城山の女神は百足として伝えられている。
3. 大蛇と百足が入れ替わる理由
この二つの神は大蛇や百足に身を変えるが、地域により、そこの住民に都合の良いものに姿を変える。これは、日本の神話や伝承にしばしば見られる「多様な地域変種(ヴァリアント)」という現象の典型例だそうだ。
老神温泉の人々にとって赤城山の神は、尊敬の対象でもあるため、敗れたとはいえ高貴な神格=大蛇として描かれている。
いっぽう、日光側では、赤城山の神は敵方=外の存在であるため、恐ろしく不吉な象徴である「百足」にされている。
蛇は日本神話で「水・霊力・変化・再生」の象徴。神に近い。また、百足は「執念・害虫・恐怖」の象徴で、しばしば敵役とされる。
つまり、同じ神話の軸を共有しながらも、地域の視点と信仰の違いによって、神の姿が変容しているというわけだ。
4. 大蛇祭り、108.22mの祭神、ギネス記録

世界一長い蛇を担ぎまわる白老温泉の「大蛇祭り」出典:産経ニュース
この故事に因んで毎年5月に、「蛇神祭(じゃしんさい)」または「大蛇まつり」が開かれている。神輿(みこし)の形は巨大な白蛇を模しており、地域の誇る伝統行事となっている。この「大蛇みこし」は、全長108.22m、重さは約2tで「最も長い祭り用の蛇」としてギネス世界記録に登録されている。地元では、この長さの大蛇が収まる建物をわざわざ構築し、内部を温泉客に公開している。

温泉客に一般公開されている「大蛇」。筆者撮影。

長~い専用の小屋に収められている「大蛇」。筆者撮影。
また、毎朝6時から地元農民が収穫した野菜や、それを農民主婦が加工調理したものを「朝市」として、大蛇の建物のある広場で行っている。
この度は、スイカや豆類、わさびドレッシング、一味唐辛子他を買ってきた。

これはホテルのお土産売り場で買った手ぬぐいの紙帯。「じゃおう」は「蛇王」か。イラストはカエルみたいだけれど、話の成り行き上、ヘビだね。
5.神社発行資料(A4表裏1色印刷)
筆者註:文面はそのままです。
5-1. 老神温泉 と大蛇まつり(表?面)
【老神温泉の歴史】
その昔、赤城山の神と日光男体山 (二荒山) の神とが今の戦場ヶ原で領地 争いをしました。赤城山の神は蛇 (へビ) に、日光男体山 (二荒山) の神は 百足(ムカデ) に姿を変えて激しく戦いましたが、蛇になった赤城の神は矢傷を負いました。
傷を負った赤城の神は、老神の地まで戻り、刺さった矢を抜き地面に刺し ました、すると温泉が漫いたのです、湧き出た温泉に浸かった蛇はみるみる傷が治癒。すぐに元気を取り戻し、見事ムカデを追いやりました。
男体山 (二荒山) の神を追い払ったことから、その温泉は「追い神」と呼 ばれるようになりました。それが今の老神温泉の名の由来と伝えられてお り、傷に効果があるとされる由縁です。
老神温泉の開祖たる蛇は、赤城の人々にとって「守り神」として信仰され ており、蛇への感謝の気持ちを込めて例年「大蛇まつり」が開催されていま す。
【大蛇まつり】
「大蛇まつり」は、「守り神」への感謝の気持ちを込めて毎年5月の第2金曜日・土曜日に開催される例祭で、赤城の神たる大蛇を神輿に仕立てて温泉街を練り歩く勇壮な祭りです。昼はかわいい子供蛇みこし、夜は大蛇を担ぐ本みこし(若衆みこし) が出で温泉街が活気にあふれます。
大蛇まっり開催の当日には、老神温泉をお授けになられた赤城の神様への感謝と、温泉を訪れる人々の無事故、幸せを願って、温泉街の赤城神社でご祈祷をうけた御神湯 (ごしんとう) を各旅館の湯船に注ぐという儀式「御神湯守の儀 (おんゆもりのぎ)」が催されます。
【赤城 神社】
老神温泉の中必部、大蛇まつりの出発点でもある赤城神社は、山岳信仰を 起源に赤城山の神を祀り、古来より人々の「守護神」として信仰されています。また、赤城神社の境内には藥師堂があり、湯禅薬師様が祀られていま す。老神を訪れたら薬師さまを詣でて、傷の治癒、美肌、病気平癒、安産、 子授け等を願いましよう。
【老神温泉の効能】
老神の泉質は、肌に優しく「美人の湯」とされるとともに「皮膚炎症」 「傷の治癒」に効くとされています。自慢の泉質に加え、御神湯を授かった お湯をゆっくり楽しみ、ますます元気に、そして美しくなりましょう。な お、蛇は元来金運にご利益があるとされていることも嬉しい話です。
■老神温泉の効能・・・自慢の泉質 (美肌、傷の治癒)
■老神温泉の伝説・・・守護神、傷の治癒、病気平癒、安産、子授け、金運上昇
5-2. 御神湯守(おんゆもり)の儀 縁起(裏?面)
【老神の湯起源】
神代の昔、赤城山の神と日光二荒山の神との間で争いが起こり、傷を負った赤城の神は老神のこの地まで追われて来ました。
この地で赤城の神が地面に矢を突くと、突然お湯がこんこんと湧き出てきました。そこで河原の石を並べ湯船を造り、その湯に入ると、たちどころに傷が治り日光の神を追い返したということです。これが追神 (老神)の湯の起源です。また、老神の湯が「赤城湯」とも言われる所以です。
【御神湯守の儀 (おんゆもりのぎ)】
この「御神湯守の儀 (おんゆもりのぎ)」は老神温泉を御授けになられた赤城の神様への感謝と、老神温泉を訪れる全ての人々の無事故を願いつつ連綿と続けられてきました。
赤城の神が湯を据り当てたとされる五月七日及び八日は、早朝よりこの刻(午前十時頃) までは湯船の周囲に七五三縄を張り廻らし、一般の人の入浴は禁止していたそうです。
さらにその儀式に加えて、各旅館でして利用している源泉を赤城神社に奉納し御祈祷を受け、その御神湯 (ごしんとう) を拝戴し各旅館の湯船に注ぐという儀式です。老神温泉のお湯が未来永劫こんこんと湧き続け、老神温泉の益々の繁栄を願い、老神温泉に関わる全ての人に幸せが訪れますよう、装いを新たに古式に做って始められた儀式です。
余談ですが、老神にはまれに瞳のない片目の蛇が来るそうです。昔の人は「赤城さまの眷属(筆者註:けんぞく)家来」と言い、危害は決して加えてはならないと伝えられています。
赤城の神様の御神徳に依り、訪れる人々がこの「老神温泉」に浴し必身の傷を癒して、身も心も健やかに御精励頂ければ幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。